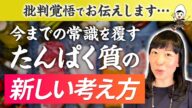James Acton, Co-Director, Nuclear Policy Program, Carnegie Endowment for International Peace
論文「本末転倒なプルトニウム政策 日本の国際政治と国際安全保障への影響」を昨年9月に発表したジェームズ・アクトン氏が日本のプルトニウム余剰問題について話し、記者の質問に答えた。
司会 杉田弘毅 日本記者クラブ企画委員(共同通信)
通訳 池田薫(サイマル・インターナショナル)
http://www.jnpc.or.jp/activities/news...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
記者による会見リポート
“余剰”プルトニウムを生まぬ具体的措置を
経済性、実現性など様々な面で課題が指摘されて久しい日本の核燃料サイクル政策。国内での認識は薄いものの、国際社会からは核の不拡散の観点で懸念が示されている。米国の政策に影響力があるとも言われるシンクタンクに所属し、核セキュリティ分野の専門家であるアクトン氏の目に日本の現状はどう映り、どんな打開策を提案し得るのか。そんな興味から会見に参加した。
アクトン氏がまず強調したのは「日本側に“余剰”プルトニウムを持たぬという国際公約を破るつもりがないことは疑っていない」ということだった。理由は、必要以上の量を抱えれば、日本の核武装を懸念する中国など周辺国との緊張が高まるし、核の潜在的な抑止力を欲する他国が、再処理の許可を米国に要求する口実とされかねないからだ。こうした事情は、安倍政権も当然認識しているはずだ、とした。
ところが、「現実は公約を守るのとは逆の方向に進んでいる」とアクトン氏は懸念する。日本は一昨年、閣議決定したエネルギー基本計画で、核燃料サイクル政策を引き続き推進することを決定。今後、青森県六ヶ所村に建設中である原発の使用済み燃料の再処理工場が全面稼働すると、年間8トンのプルトニウムが生み出される。「これを消費するには16から18基の原子炉でMOX燃料を燃やす必要があるが、原発の再稼働の状況を考えると難しい。消費しきれず、毎年約4トンずつ備蓄が増えていくだろう」という見通しを示した。
その上でアクトン氏が提案したのが、再来年に改定時期を迎える日米原子力協定を延長し、新たに付帯決議を設けることだ。この決議の中で、日本が再処理工場の稼働を事実上遅らせるとともに、毎年消費できる分と同量しか抽出しないよう再処理量を調整することを約束する。また、5年間に消費できる分を超えた量を“余剰”とみなすなど、余剰分の定義を明確にする。50トン近く溜め込みながら、『いずれ使うから余剰ではない』と主張しても不信を買うだけだからだ。こうした具体的な措置によって、必要以上の量を持たないという公約を担保するべきだという。
さらにアクトン氏は使用済み燃料を再処理せずに直接、地層処分する方法についても将来の選択肢として同時に検討を進めるべきだとする。
ただ、仮に提案を実行に移す場合、青森県の理解をどう得るかが最大の壁だ。アクトン氏も指摘するように、福島の事故後に政府が再処理政策の見直しを一時議論しながら最終的に断念したのは、青森県の強い反発があったからだ。過去に再処理を委託した英仏から高レベル廃棄物が返還されることをめぐり、保管施設がある青森県が輸送船の入港拒否をちらつかせれば、国際問題になることを恐れる政府にとって無視はできない。
核不拡散をめぐる国際社会の厳しい視線と、地元・青森県との関係。この相矛盾し複雑な国内外の状況をどう解きほぐし、現状を打開していくべきか。メディアが議論を広く喚起していく必要性を改めて考えさせられる機会となった。
NHK報道局科学・文化部
本木 孝明
powered by Auto Youtube Summarize