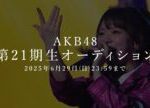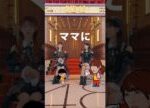2023.03.19
117系 廃車回送
#廃車回送
117系電車(117けいでんしゃ)は、日本国有鉄道(国鉄)が製造した直流近郊形電車。
1979年(昭和54年)から1986年(昭和61年)にかけて216両が製造され、国鉄分割民営化の時には東海旅客鉄道(JR東海)に72両、西日本旅客鉄道(JR西日本)に144両がそれぞれ承継された。
京阪神地区の東海道本線・山陽本線で運行している新快速には、1972年(昭和47年)からそれまでの113系に代えて、山陽新幹線岡山駅開業に伴い余剰となった急行形車両153系が投入されていた。元来は長距離の急行用車両であったため冷房装置を搭載し、乗り心地の良い空気ばね台車で、洗面所やトイレ付きで座席は比較的ゆったりしていたとはいえ、デッキ付きの乗降口を両端に有する構造は快適ではあってもラッシュ時の輸送に難点があった。また、製造初年が1958年(昭和33年)と古く、ボックスシート(固定クロスシート)であり、京阪間を運行する阪急電鉄や京阪電気鉄道の転換クロスシートを備えた特急車両(阪急6300系・京阪3000系)に比べると見劣りしていた。
117系はこれらの課題点を踏まえ、京阪神地区の輸送事情に適合する車両として設計された。客室設備は1975年(昭和50年)に北九州地区に投入されたキハ66・67系を基本とし、急行形を上回る設備水準の車両として構想され、それまで一貫して車両の標準化を推進してきた国鉄が地域の事情に応じて設計、製造した嚆矢となっている。
本系列による新快速には153系時代の「ブルーライナー」に対して、「シティライナー」という新たな愛称が与えられた。さらに、1982年(昭和57年)には東海道本線名古屋地区の快速に使用されていた153系の置換え用として、「東海ライナー」という愛称で投入された。
車体
全長20 mで、各種の腐食対策が施された鋼製車体に片側2か所の半自動対応の両開扉を設置する。湖西線での運用を考慮して、耐寒・耐雪仕様(関西地区投入分)とされている。
屋根部分は張り屋根となっており、車両妻面上部には押え用金具を確認することができる。車体番号は、車両側面にステンレス製の切り抜き文字を張り付けている。
外観から見た側面の構造は先行するキハ66・67系に類似しており、戸袋部を除いて2段上昇式の窓を2セットずつ1組としたユニット窓が並ぶ。このため、窓配置は制御車がd1(1)D(1)2222(1)D(1)2(d:乗務員扉、D:客用扉、(1):戸袋窓)、中間電動車が2(1)D(1)2222(1)D(1)2という独特の形態である。
客用扉窓および戸袋窓に設置するガラスの支持方式を、従来のHゴム式から押え金式に変更した。
前面形状も独自のもので、157系に類似する「鼻筋」の通った流線形の構体に高運転台、左右各2灯を腰部に備えた前照灯、中央窓下に設けられた列車種別表示器とタイフォン(警笛)と従来にないデザインとなっている。
塗装はクリーム1号を基本とし、ぶどう色2号の細帯が窓下に入る構成である。この2色塗装は新快速のルーツである急行電車に使用されていた52系や、戦後の1950年(昭和25年)に製造された80系の塗装に類似した、大阪鉄道管理局伝統のカラースキームに則った塗色が選ばれている。従来、国鉄の近郊形電車は電気方式が同じであれば同一の塗装を施すルールとなっていたが、本系列ではそのルールを打破して系列専用色が採用され、以後、105系などで地域固有色が採用される先駆けとなった。
冷房装置は国鉄標準のAU75B集中式冷房装置(冷凍能力42,000 kcal/h)を屋根中央に搭載するが、その前後にキハ183系や781系などと同様に新鮮外気導入装置を設置している。そのため、従来の車両に取り付けられていた押込式通風器は廃止されている。
座席は転換クロスシート(一部固定)でつり革は一切設けられず、車内妻面の化粧板を木目調仕上げとして、さらに蛍光灯には乳白色のグローブ(カバー)が取り付けられるなど、近郊形電車としては破格の高級感を演出している。車内は禁煙区間のみ運用されていたが、臨時列車での使用や禁煙区間外での運用を考慮して、中間車のみ灰皿を設置している。
天井は平天井となったが、両隅(荷棚上部)に境目があり角張っている。この処理は製造初年が近い781系や185系も同様であり、本系列以前では新幹線0系や京成AE車にも見られた特徴である。また、編成中に1か所、和式トイレを備える。
なお、当初計画された車体は前面形状が異なり、客用ドアは実際に採用されたものより各々910 mm車端寄りにあり、車体塗色は711系に倣い赤2号にクリーム4号で、車端部にロングシート、室内化粧板は薄茶色6号、屋根に押し込み式通風器があるというキハ66に近いものであった。
主要機器
設計当時の標準品を多用しているが、最高速度が従来の近郊形電車の標準である100 km/hから110 km/hに引上げられた関係から、その多くは上位機種を採用している。
MM'ユニットを採用し、M車(モハ117形)には主制御器・抵抗器 (MR136)・集電装置が、M'車(モハ116形)には電動発電機・電動空気圧縮機が搭載される。
主制御器は CS43 の流れを汲み、信頼性と保守性を考慮して417系で使用し実績のあった電動カム軸式の CS43A で、抵抗制御と直並列制御を組み合わせて加減速を行う。勾配抑速ブレーキや条件が整っていれば並列段からの再加速が可能である。本系列には、カム軸機構の改良などにより内部動作の多段化が行われスムーズな加速を可能とした、当時最新のCS43Aが採用されることになった。主制御器1基で2両8基分の主電動機を制御する1C8M方式である。主電動機は当時の国鉄電車の標準機種の一つであり、113系などと共通の直流直巻式整流子電動機であるMT54Dを装備し、歯車比も従来の近郊形と同様の1:4.82とされた。実用域の高速性能は153系と同等で、起動加速力は上回り勾配線区にも対応している。
制御用や冷房用電源として、東芝が原設計を担当した電動発電機 MH135-DM92 を採用する。103系や113系・115系などで採用された実績のあるタイプであり、集電装置からの直流1,500 Vを電源として三相交流440 V 60 Hz(定格容量160 kVA・4両給電)を出力する。
空気圧縮機は、集電装置からの直流1,500 Vを電源とした2段圧縮直結駆動式の MH113B-C2000M を搭載する。
台車は高速走行時の走行特性やDT24系空気ばね台車を装着していた153系からの置き換えであることなどを考慮し、特急・急行形で使用実績のあるインダイレクトマウント空気ばね台車であるDT32E(電動車)・TR69H(制御車)を採用した。
集電装置は設計当時に直流形電車の標準品であったPS16系菱形パンタグラフであるが、アルミニウム製の枠を使用し、湖西線での運用を考慮してばね部分にカバーを施した耐寒・耐雪仕様のPS16Jが採用されている。
連結器は国鉄標準の柴田式密着連結器を採用するが、153系の運用形態を踏襲し、ラッシュ時に6両編成を2編成組み合わせて12両編成で運用する計画であったことから、増解結作業の容易化のために、連結器には国鉄初となる自動解結装置と電気連結器が採用された。
JR化後
国鉄分割民営化に際しては、京阪神地区への投入車は全車JR西日本に、名古屋地区への投入車は全車JR東海に承継された。
JR西日本
JR西日本発足時、144両(6両編成24本)が宮原電車区に配属されていた。
1988年3月13日ダイヤ改正で運用範囲を彦根から米原まで延長し、翌1989年3月11日ダイヤ改正では朝ラッシュ時間帯に2編成連結した12両編成「新快速」での運転を開始した。しかし、同時に221系が登場し、徐々に新快速での運用を縮小することとなる。1990年3月10日のダイヤ改正から新快速の最高速度を115 km/h[注 18]に引き上げた。また、新たに福知山線(JR宝塚線)での運用を開始することになり、48両(6両編成8本)が福知山色(クリーム10号に緑14号の帯)に塗装変更された。
1991年3月16日ダイヤ改正では早朝深夜を除いて新快速の最高速度が120 km/hとなった関係で、新快速運用は米原 - 大阪と大阪 - 野洲の2本のみ[24]に縮小したことから、6両編成10本(C11 - C20編成)を8両編成5本と4両編成5本に組み替え、4両編成は奈良線快速に、6・8両編成は米原 - 網干・播州赤穂間の快速列車に充当した。同年9月14日に北陸本線(米原 - 長浜間)の直流電化切り替えが完成したことから、運用範囲が長浜まで拡大している。
1992年3月14日ダイヤ改正では、岡山・広島地区の115系非冷房車置き換えと岡山地区の快速「サンライナー」(岡山地区への転用を参照)充当のため岡山電車区・広島運転所(現・下関総合車両所広島支所)へ転属した。サンライナー向けに投入する編成は4両編成であり、その他組み替えで発生した電動車11組22両の余剰車を115系へ改造し組み込み115系非冷房車を置き換えた(115系3500番台への改造を参照)。これにより、117系として初めて車両数が減少した。また、福知山線(JR宝塚線)の混雑対策として、一部座席のロングシート化改造が行われた。
新快速用に残った117系も、乗客増加により2扉車は不向きとなり、120 km/h運転に対応できないことから同改正以降の新快速運用は原則的にダイヤと輸送力に余裕がある朝晩のみ、それも大阪 - 京都方面間限定とされた。1999年5月11日ダイヤ改正で、新快速の130km/h運転が開始(西明石 - 草津間)されることとなり、本系列の定期新快速運用が終了した。2001年には広島地区の115系初期車の置き換えを目的に、中間車6両が115系へ追加改造され、総数は116両に減少した。
2016年現在、原形をとどめるのは、吹田総合車両所京都支所(旧:京都総合運転所)の8両編成2本16両のうちの12両。残り4両にはトイレの増設とバリアフリー対応化改造が行われた。2004年10月10日に「リバイバル新快速」として、限定運用ではあったが再び新快速運用に充当された。また、2009年4月には湖西線の臨時列車で再び新快速運用に充当された。
しかし他線区へ転用された車両も、福知山線(JR宝塚線)では221系による丹波路快速が2000年3月11日に運転が開始されたことによって運用が削減。奈良線では2001年3月3日から221系によるみやこ路快速の運転開始に伴って運用が終了する一方、紀勢本線・和歌山線・山陽本線下関地区で運用が開始するなど、運用範囲の変化が発生している(下関地区では2016年1月、紀勢本線・和歌山線では2019年3月に運用終了)。
長らく、115系への改造車を除く116両全車が在籍していたが、2015年より廃車が開始され、2022年10月現在は53両が在籍している。
ウィキペディアより
#jr西日本 #117系 #国鉄
powered by Auto Youtube Summarize